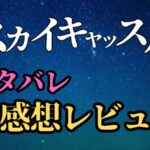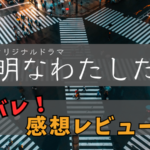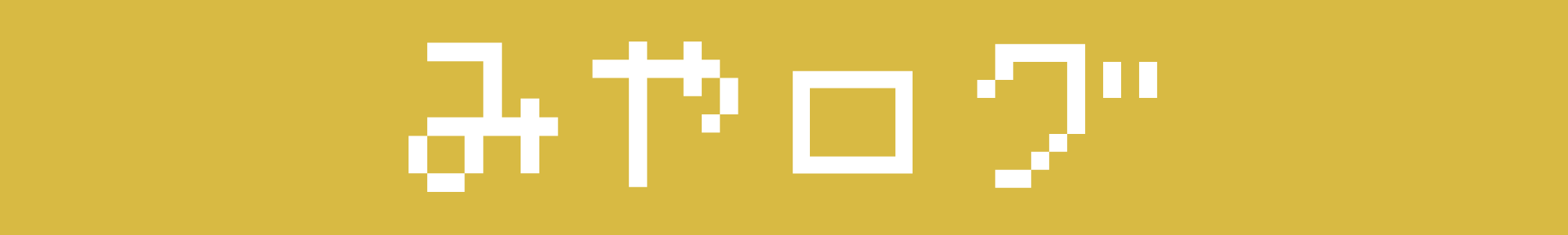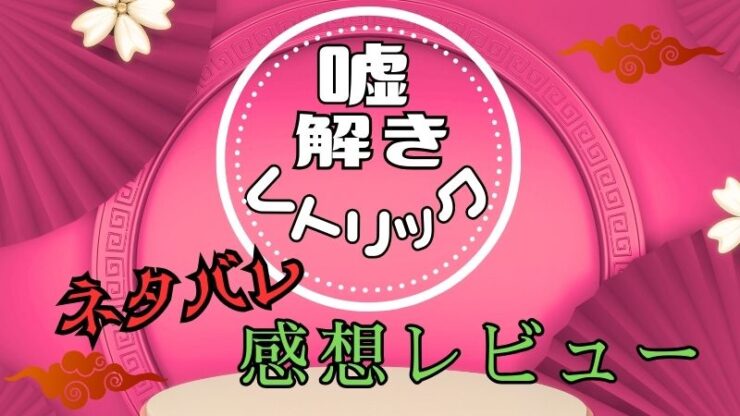
【原作】都戸利津『嘘解きレトリック』
【脚本】武石栞、村田こけし、大口幸子
【演出】西谷弘、永山耕三ほか
【キャスト】鈴鹿央士、松本穂香、味方良介、杉本哲太、若村麻由美ほか
【あらすじ】
時代は昭和初期の日本。
田舎の村に暮らしていた浦部鹿乃子(松本穂香)。
彼女は「人の嘘がわかる」という特殊能力を持っていた。
そして、その特殊能力のせいで、村の人間からは「気持ち悪い」などと言われ嫌われていた。
母・フミ(若村麻由美)にも迷惑がかかると思い、村を出て行くことを決意した鹿乃子。
鹿乃子は九十九夜町(つくもやちょう)という街に行き着く。
待ちゆく人の「嘘」に辟易しながら、働き口を探していた鹿乃子だったが、なかなか職が見つからない。
一方、九十九夜町で『祝探偵事務所』を営む祝左右馬(鈴鹿央士)は、友人であり警察官の端崎馨(味方良介)を連れ、稲荷神社の掃除に来ていた。
実は家賃を支払えないほど貧乏な状況の左右馬は、大家が管理している稲荷神社を清掃することで、家賃をまけてもらおうと思い、掃除の手助けとして馨を連れて来たのであった。
掃除をしようとしていた左右馬の耳に、獣の唸り声のようなものが聞こえてきた。
何事かと音のする方へ駆け寄ると、空腹に耐えかねた鹿乃子が、猫とメザシを巡って対峙していたのであった。
「なんだ」と呆れて帰ろうとする左右馬だったが、空腹で力尽きた鹿乃子は倒れてしまう。
倒れた鹿乃子を、左右馬と馨で「くら田」まで運んでいき…。
もくじ
【ドラマ】嘘解きレトリック ネタバレ!感想レビュー(1話)
原作に忠実
マンガ原作の本作。
ピッコマで原作マンガの1話が無料で読めるので、ドラマを観た後に読んでみた。
すると驚くべきことに、1話に関していえば、鹿乃子が九十九夜町に来てからの登場人物のセリフや、鹿乃子の心の声、それぞれのキャラクター設定、さらにカット割りまで全てが原作を忠実に再現していた。
昨今の原作改変とは打って変わって、原作へのリスペクトがすごい。
ここまで忠実に再現してくれていれば、原作のファンも喜ぶこと間違いなしだろう。
セットの作り込みもスゴイ
予算削減が強いられているであろう昨今のテレビ業界。
もちろんドラマ制作もその影響を受けていることだろう。
時代劇ものをやるとなると、その当時の街並みを再現したセットを組まなければならなかったり、地方の山でのロケ、さらに和物の衣装の用意など、現代劇よりも圧倒的に予算が必要となるはず。
そのため、昨今のドラマで時代劇ものはなかなか作られていないか、作られてもチープなものになりがち。
しかし『謎解きレトリック』は、セットもしっかりと作り込みがされていてチープ感が一切ない。
衣装も和モダンのお洒落な感じでとても良い。
キャスティングは、地味だが原作に合っていて実力も伴っている
たとえ作られたとしてもキャスティングに予算が割けなくなる傾向もある。
今回も主演に抜擢された二人、鈴鹿央士さんと松本穂香さんは、タレントパワーで言えばまだそんなに高くないはず。
さらに、3番手に名前のある味方良介さんや、4番手に名前のある片山友希さんも知名度は高くないはずです。
言葉を選ばず言えば、月9にしてはだいぶ地味である。
しかしこの地味さが昭和初期にピッタリ合っている気がします。
特に松本穂香さんは、原作マンガの鹿乃子そのもののよう。(原作では鹿乃子は16歳で、松本さんの実年齢は27歳ですが、そこまで違和感ないように思います。)
個人的に、メインの4人は若手ながら実力がしっかりあるので、ドラマの完成度としては高い物になるのでは?と期待しています。
視聴率では苦戦を強いられそうですが…。
内容も面白い。けど実写としての魅せ方もほしい
人気のマンガが原作で、内容も忠実なので面白かったです。
1話は時代背景や人物紹介などがあるため、謎解き要素は少なめ。
それでも、物語の中に小さな伏線がたくさんあって、「ああ!そこが繋がるのか!」と感心しました。
ただし。
マンガを忠実に再現することで、若干の違和感があります。
マンガって、過剰にコメディーチックだったり、ノリツッコミが多かったりしますよね。
それを現実の世界で再現すると、なかなかシュールに映る時があるんですよね。
特に今回で言えば、左右馬と馨のノリツッコミ。
二人のしょうもない掛け合いは、マンガで見るとよくある光景なのですが、実際に大人の男二人が言葉として発しているとシュールに映ってしまう。
また、マンガだと「心の声」が多用されますが、今作ではこれも完全再現しています。
マンガだと細かなニュアンスを人物の雰囲気だけでは表現しきれないため、「心の声」が多くなる傾向があります。
通常、ドラマや映画にするとき、この「心の声」がカットされることが多い(と思います)。
そのかわり、セリフを足したり、人物の行動を原作から変えて、その人の心情を「心の声なし」で表現しようとするのだと思われます。
結果的に原作は改変されてしまうわけです。
今回は「心の声」をそのまま活用したため、登場人物のセリフや行動も、原作のままで問題ないため、原作を忠実に再現できたのだろう思います。
個人的には、ドラマで「心の声」が多用されるのはあまり好きではないです。
というのも、「心の声」が入ると物語の進みが滞る気がするのです。
「もう分かったからはやく話進めてよ!」という気持ちになっちゃうんですよね。
例えば、男がふいに「好きだよ」と言ったことに対して、女はびっくりして「何言ってんの!」と慌てます。ちょっとドギマギしてる様子で相手の顔を横目でチラ見しちゃう女。というシーンがあったとします。
観てるこちらは(ああ、照れてるんだな)とわかりますよね?
もしそこに「心の声」で『ちょっとちょっと!急に何言ってんの?!どうしていきなり…。え?私、もしかして試されてるー??』のような心の声で、気持ちの説明が入るとどうでしょう?
(いちいち言わなくてもわかるよ)
という気持ちになりませんか?
「心の声」で気持ちを表現しようとすると、こういうノックが起こる気がするんですよね。
『謎解きレトリック』でもそれがけっこうありました。
内容として間延びしてるわけではないんだけど、「なんか展開の進みが遅くて長いな~」という気持ちになってしまったので、2話以降はどうなっていくかやや不安…。
原作をやや改変してドラマ制作側としての魅せ方にこだわるよりも、原作に忠実であることをとった今作。
それが吉と出るか凶と出るか。
いずれにしても、原作に忠実である方が、原作者の方としては嬉しいに決まっていますが。
【ドラマ】嘘解きレトリック ネタバレ!感想レビュー(2話)
好き嫌いが分かれそう
鹿乃子の「嘘がわかる」という特殊能力は、ファンタジー感を演出しているので、そういうのが好きな人には好まれると思う。
しかし、謎解きミステリーとして楽しみたい人にとっては、誰が嘘をついているか分かってしまうと、全ての謎が解けたときの感動が減少してしまうというものだ。
かくゆう私は、謎解きミステリーとして楽しみたい派。
そのため、謎解きの面白さは…正直ちょっと物足りない。
今回の話をざっとまとめると、
車で舞台鑑賞に出かけたお嬢様。
しばらくすると運転手の男が頭から血を流して戻ってくる。
運転手の男が襲われ、その隙にお嬢様が誘拐されてしまったらしい。
運転手の男は犯人から「娘は誘拐した。身代金を用意しろ!」という紙を手渡され、急いでお嬢様の家に駆け戻り、身代金を用意するよう伝えます。
しかし!実はこの誘拐事件、運転手の男がでっちあげたものだった。
つまり狂言誘拐だったのだ!
実際はお嬢様は誘拐などされておらず、お嬢様が舞台を鑑賞している間に誘拐事件をでっち上げることで、身代金を奪おうとしたのだった…!
こんな感じ。
まるで小学生の時に読んだ、学園ミステリーの小説のような内容…。
小説やマンガとして読む分には面白いのかもしれないが、ドラマとしてやろうとすると、ややチープになってしまう。
「ほんわかファンタジー」として見れば申し分ないが、本格ミステリーとして楽しむには、やっぱり物足りない気がする。
少しずつ謎解きミステリー度が上がっていくことに期待したい。
【ドラマ】噓解きレトリック ネタバレ!感想レビュー(3話)
左右馬と鹿乃子のほんわかさが癒される
左右馬と鹿乃子のほんわかバディーを楽しむのが、このドラマの醍醐味かもしれない。
「嘘が見える」という鹿乃子の特徴を、左右馬が一生懸命探ろうとしたり役立てようとすることで、鹿乃子は徐々に「嘘が見える」ことに対する後ろめたさがなくなってきたように見える。
謎解きミステリーとして楽しもうとすると少々物足りないが、ほんわか仲良し探偵事務所のお話として見る分には癒されてちょうど良い。
3話に「謎解き」はない
今回の話のメインは、左右馬の親友で刑事の馨が探している「松葉牡丹」の君が誰なのか?ということだった。
ざっと話をまとめると、
馨が「松葉牡丹の君」と遭遇したのは、左右馬から渡された九十九焼きを食べ、腹を壊していた時のこと。
腹痛に苦しむ馨のことを、通りすがった「松葉牡丹」の襟の女性が介抱してくれたのだった。
後日。
馨は職場のデスクで、たまたま開かれていた雑誌に目が留まる。
そこには、『60番街の老舗料亭』に勤める従業員らの集合写真が写っていた。
そしてその中でひと際美しい女性が、「松葉牡丹の君」ではないか?と馨は思った。
すぐさま馨は左右馬の元に訪れる。
実は左右馬は、「松葉牡丹の君」をしっかりと見ていたのだ。
馨は左右馬に件の雑誌を見せ、「松葉牡丹の君はこの人ではないか?」と尋ねる。
しかし左右馬は「この人じゃない」と嘘をつく。
実は左右馬は、「松葉牡丹の君」についてある事実を知っていた。
それは、馨を介抱していた「松葉牡丹の君」が、馨の胸ポケットから財布を盗もうとしていたことを…。
その事実を知っていた左右馬は馨を思い、「松葉牡丹の君はこの人ではない!」と嘘をついたのだった。
つまり今回は全く「謎解き」ではない。
「松葉牡丹の君」と思しき女性の写真をたまたま見つけたのは馨であるし、「松葉牡丹の君」が盗人である事情を左右馬は知っていたわけで。
ただただ、「親友を守るために左右馬が優しい嘘をついた」というお話だった。
噓解きレトリック ネタバレ!感想レビュー(4話)
あらすじ
九十九夜町、早朝の目抜き通りで祝左右馬(鈴鹿央士)と浦部鹿乃子(松本穂香)が駅に向かっている。汽車に乗ってお出かけとはしゃぐ鹿乃子に、左右馬は、“家賃を払えず、朝だけど夜逃げをしているだけ”と教えた。
そんな時、左右馬が不審な男に気づき、鹿乃子の“嘘(うそ)を聞き分ける能力”で置引を暴く。
男は逃げるが、居合わせた女性に足を引っ掛けられて転び、周囲の人たちに取り押さえられる。
置引犯に足を掛けた女性は左右馬の知り合いで、端崎馨(味方良介)の姉・雅(北乃きい)だった。
左右馬たちが夜逃げ中だと知った雅は、取材旅行に同行しないかと2人を誘う。
雅が『魔境探報』という怪談雑誌の記者と聞いた鹿乃子は怯え、左右馬も断ろうとするが、今月分の家賃を報酬にすると言う雅に、左右馬が即座に快諾した。
雅が取材するのは「人形屋敷」と呼ばれる綾尾家。
綾尾家には、生まれつき体の弱かった一人娘の成長を祈願し、娘の成長に合わせて作った人形を娘と同様に育てるという変わった風習があった。
屋敷は現在、主人夫妻が海難事故で亡くなり、一人娘の品子(片岡凜)が継いでいる。
品子の姿はまるで人形のようで、妙な噂もつきまとっていた。
そんな中、現地に到着した左右馬ら一行を柴田(佐戸井けん太)が案内する。
柴田によると、女中のイネ(松浦りょう)が、屋敷の「人形部屋」をのぞくと、誰かの死体を発見。
イネは慌てて柴田の家に飛び込んできたが、柴田が刑事の寺山清一(正名僕蔵)とその部屋へ行くと死体だと思われていたのは人形で、その後イネが岩場に落ちて死んでしまったという・・・。
事件の真相を突き止めるため、左右馬、鹿乃子、雅が品子と会うと・・・。
引用元:Tver
今回はしっかり「ミステリー」
2話・3話と、街中で起きるちょっとした問題をあっさり解決するだけだったので、正直「このままこういう調子の話だったら、もう観ていられないかも…」と思っていたが、4話はちゃんとミステリーっぽくなってきました!
「山の中にある不気味な噂がつきまとう屋敷」「人形にまつわる奇妙な風習」「なぜか長続きしない女中」「人形を持ちながら川で亡くなっていた女中」
ミステリーはやはり「風習」「災い」「呪い」などが入ってくるとがぜん面白くなってくる。
今回は「娘の成長に合わせて作った人形を娘と同様に育てる」という奇妙な風習。
品子は双子なのか?
「品子さんは双子ですか?」と鹿乃子が問うと、「いいえ」と否定する品子。そこに嘘はなかった。
しかし、品子と共に母屋で食事中、品子の部屋には確実に何者かがいた。
「双子ではない」けど「もう一人」いる。
そしてその存在は隠されている。
さらに、「今回綾尾家で亡くなった人間はいない」「女中のイネは自殺だった」という品子の言葉は嘘だった。
もしかすると品子は三つ子?
三つ子だとすれば、「双子ですか?」という質問に「いいえ」と答えても嘘ではない。
・通常、表に顔を出すのが品子A
・離れでご飯を食べ、ラストシーンで左右馬の前に現れた口調の荒い品子が、品子B
・殺鼠剤を食べて亡くなったのが品子C
と考えればつじつまが合う。
昭和初期において三つ子は、おそらく「隠すべき」こと。
人形と共に育てるという独自の「風習」を作ることで、食べ物・着物など、およそ一人娘の分量とは思えない数をこしらえても、「人形のため」と言えば丸く収まる。
はたして真相は一体…?
次週も「人形屋敷編」は続くので楽しみだ。
嘘解きレトリック あらすじ&ネタバレ感想レビュー(5話)
5話 あらすじ
祝左右馬(鈴鹿央士)と浦部鹿乃子(松本穂香)は、端崎馨(味方良介)の姉で怪談雑誌の記者・雅(北乃きい)の取材に同行する事となった。
取材のネタは「人形屋敷」と呼ばれている綾尾家で起きた“人形殺人事件”。
1ヶ月前、綾尾家の使用人・イネ(松浦りょう)が不審死していたのだ。 綾尾家には両親を亡くした品子(片岡凜)という娘が、使用人たちと住んでいる。離れの「人形部屋」は品子の部屋となっており、そこには綾尾家にまつわる奇妙な噂の元となる数々の人形が置いてあった。
品子に会った雅は、事件当時の状況を聞く。
鹿乃子は品子の「うちは誰も死んでいない。イネさんは自殺」との言葉がウソであることに戸惑う。
左右馬と雅も品子の話の端々に違和感を覚えていた。
翌日、左右馬と雅が離れ屋に向かうと、格子戸越しに見える障子に血飛沫が飛んでいるのに気付く。
左右馬たちが慌てて部屋に入り、品子が倒れていると思って触れたのは人形だった・・・。
そこに品子が現れた。品子の着物には血が滲んでいる。そして鹿乃子も合流する。
雅から着物についた血の原因などを聞かれて答える品子だが、鹿乃子はその返事がウソだと分かる。
さらに、左右馬との会話の中でも品子のウソを聞く鹿乃子。
鹿乃子からウソの合図を受け取った左右馬は、いつになく真剣な表情で、警察と医者、そして自動車をすぐさま手配するよう女中に頼んで…。
引用元:Tver
謎解きクイズ!
結果、予想通り品子は三つ子だった。
普段察しの悪い僕が、いともたやすく推理できたということは、おそらく視聴者のうち8割方は予想できた謎だったに違いない。
「双子じゃない」ということが本当だとすれば「三つ子」って謎解きクイズありそう。
うん、きっとある。
絶対ある。
謎解きゲーム『レイトン教授』の中にあった気がする!
お子様から大人まで楽しめる謎解きゲーム『レイトン教授』を思い出させてくれる本作に感謝したい
本作を観るうえで「難解な謎を解きたい!」「種明かしが楽しみ~!」というような感情をもつことは、野暮というものである。
「本当の自分を隠さず生きよう」がメインテーマ
「謎解き」をメインと考えるから、その単純さに拍子抜けするだけ。
「本当の自分を隠さず生きよう!ということを作家は伝えたかったのだ」と捉えれば、それなりに考えさせられる内容の話しだったなと思えた。
【品子たちが隠れて生きていた経緯】
品子たちの母は双子だった。
ところが品子たちの母が育った村はかつて、双子が生まれると「災いを呼ぶ」と恐れられ、双子のうちの一人を殺してしまう風習のあった村。
時代的にさすがにその風習はなくなっていたものの、双子が生まれた家は後ろ指を指されることになるのは避けられなかった。
品子たちの祖母は精神的に耐えられなくなり、双子の一人を道連れに心中した。それも残された一人の目の前で…。
目の前で母と姉妹の死を見た品子たちの母だったが、やがて結婚し子を孕んだ。
しかし、そのお腹の中の子が三つ子とわかった途端、品子たちの母は精神を病んでしまった。
そこで品子たちの父は、母の育ってきた村とは全く縁のない場所へ引っ越した。
そして、産まれてきた三つ子の存在を世間から隠すため、「人形を育てる」という嘘の風習を作り上げた品子たちの父。
やがて品子たちの母は、品子を1人娘だと思いこむようになっていった…。
「なぜ自分たちは3人で1人の品子を演じなければいけないのか?」
その理由を何も知らなかった品子たちは、ただただその教えを守るしかなかったのだった。
3人で1人の「品子」として生きなければいけなかったとき、3人は本当の自分を隠さなければいけなかった。
そして鹿乃子もまた、「嘘が見える」という能力を公にすると、他人から気持ち悪がられるため、自分を隠して生きてきた。
周囲の目を気にして自分を隠して生きなければいけない苦しさ。
自分を認めてくれる人に出会ったりして、自分らしく生きられるようになった喜び。
そういったものを教えてくれる回だった。
嘘解きレトリック あらすじ&感想レビュー(6話)
6話 あらすじ
九十九夜町で探偵業を営む祝左右馬(鈴鹿央士)の探偵助手となった浦部鹿乃子(松本穂香)。
鹿乃子は助手として“早く先生の役に立ちたい”と思っていた。
そんな中、事務所の大家が鹿乃子に猫探しを依頼。無事に猫を発見するも、家賃をまけてもらえないか、金にならないかと猫を交渉材料として考える左右馬にあきれる鹿乃子。
そんな2人が事務所に戻ると、藤島千代(片山友希)を見つける。
「関わると、ロクなことがない」と逃げる左右馬は、鹿乃子と若竹座のお練り(祭礼の行列)に紛れ込んで身を隠す。
だが、知り合いに声をかけられた左右馬を千代が発見。
左右馬の方に駆け寄ろうとした千代は男とぶつかって倒れてしまう。
男は千代に怪我がないか確認すると去り、鹿乃子は千代が落としたカバンなどを拾う。
そして、着崩れた千代の着物を着付け直すために事務所へ行くことになった。
着付けを終えた千代は、探偵事務所に興味津々。事務所の様子をメモしようとカバンを開けると、見知らぬ手鏡があった。
先ほどぶつかった時ではないかと推測する千代は男に手鏡を届けに行こうと言い出す。
左右馬は男の当時の装いなどから、左官屋さんではないかとアドバイスし、鹿乃子を千代に同行させる。
千代は“少女探偵団結成!”と喜び勇んで事務所を出発する。
早速、左官屋をあたった鹿乃子と千代は、利市(橋本淳)ではないかと教えてもらい、無事に利市に手鏡を返すことができたのだが、その後、周辺でひったくり事件が発生していることが発覚。
「若い男に手鏡を盗まれた」という女性に手鏡の特徴を聞くと、利市が持っている手鏡と一致、鹿乃子と千代は利市をひったくり犯として再び捜索する。
引用元:Tver
自信過剰になると視野が狭くなる
ということが6話のテーマではないだろうか?
1話では「嘘が見える」自分の特殊能力を嫌がっていた鹿乃子でしたが、左右馬と関わるうち、次第に「自分の能力は使い方次第で人の役に立つ」と思えるようになってきた鹿乃子。
人形屋敷の一件で、すっかり自信をつけた鹿乃子は左右馬の力を借りずに、自分の能力を活かしてみようと奮闘しようと試みます。
拾った手鏡の持ち主が利市とわかり、返しに行く鹿乃子と千代。
利市は手鏡を見て「俺の手鏡!」と言いますが、その言葉に嘘はありません。
安心して手鏡を利市に渡すと、「これお母ちゃんの形見なんだ」と発する利市。しかしその言葉は嘘だった。
「俺の手鏡」は本当で、「母の形見」は嘘。
利市に違和感を覚えつつもその場を後にする鹿乃子。
その後、甘味屋でおやつを食べていた鹿乃子の耳に、「この間ひったくりにあって手鏡を盗まれたのよ」と語るご婦人の話が入ってきます。
盗まれた手鏡。
手鏡を見て母の形見だと嘘をついた利市。
二つの情報から、「ひったくりの犯人は利市」と思いこんでしまった鹿乃子。
しかし結局、利市に返却した手鏡と、ご婦人が「盗まれた」と言っていた手鏡は全くの別物だったことが判明。
利市はひったくりなどしていなかったのだった。
鹿乃子は「嘘が見える」という能力を過信しすぎるあまり、「利市が嘘をついている」という情報だけで、彼がひったくり犯だと決めつけてしまったのでした。
自分の能力を信じすぎて、ほかに見るべき大事なことを見落としてしまう。
よくある勘違いですよね。
でも、そうやって失敗を重ねないと気づけないこともあるわけで。
やってしまった過ちは反省して次に生かす。
相変わらずミステリー要素は薄いですが、人生の教訓は色々学べる良いドラマですね。
嘘解きレトリック あらすじ&感想レビュー(7話)
7話 あらすじ
祝左右馬(鈴鹿央士)と浦部鹿乃子(松本穂香)がお食事処『くら田』で昼ご飯を食べていると、疲れた顔をした端崎馨(味方良介)が来る。
一昨日、三十三番街で発生した強盗殺人事件を担当する端崎だが、その捜査が難航していたのだ。
話を聞いていた倉田達造(大倉孝二)が三十三番街の裏にある三十番街には「幽霊屋敷」があるのではないかと反応する。
その屋敷では10年前に住んでいた足立画伯が妻を殺害して行方不明。
殺害された妻の幽霊が出るといううわさがあった。
そんな時、ヨシ江(磯山さやか)が病院にショールを忘れたことに気づく。
鹿乃子は「いつもタダでご飯を食べさせてもらっているので」と病院に取りに行くことを申し出た。
それを聞いた達造が夕食にサービスの食材を追加すると言うと、左右馬も同行する。
左右馬と鹿乃子が病院でショールを受け取ると、なにやら病室が騒がしい。
病室では「カフェーローズ」で働く女給のリリー(村川絵梨)が男を厳しく問い詰めていた。
リリーが問い詰めていたのはカフェーの常連客・桐野貫二(黒羽麻璃央)。
一昨日の夜、リリーと貫二は映画を見る約束をしていたが、貫二が時間になっても現れず、約束をすっぽかしていた。
貫二は映画館に向かっている途中、三十番街の「幽霊屋敷」で女の幽霊を見て、驚いた拍子に転んで骨折し、そのまま入院しているという。
一方、映画館で貫二を待っていたリリーは、貫二と一夜を共にしたという女性(坂東希)に声をかけられており、その女性が貫二を探しているということで、約束を破った浮気者と腹を立てていたのだ。
鹿乃子は貫二の言葉にウソがないことが分かると、左右馬に合図。
その夜、左右馬たちは「幽霊屋敷」へ向かう。
引用元:Tver
ちゃんとしたミステリー
今回はちゃんとした謎解きミステリー回でした!
・殺されたご隠居
・妻を殺害した後行く不明になっている画伯
・幽霊屋敷となった画伯の家にいた女の幽霊
・女の幽霊を目撃した絵描き
・絵描きの男と待ち合わせをしていたリリー
・絵描きの男を待つリリーの元に「これあなたよね」と言って、絵描きの男が描いた「リリーの絵」を見せる謎の女…
色んな謎の伏線が張り巡らされ、最後にはしっかりと全部回収していく気持ち良さ…。
これぞ謎解きミステリーの醍醐味!という感覚を、7話目にしてやっと満足に味わうことができました!
「『噓解きレトリック』で満足感のある謎解きミステリーを楽しみたい方は、どうぞ7話がオススメですよ~』と広め歩こう。
見えた「嘘」に向き合う鹿乃子
1話~6話までのサイドテーマ…いや、もはやメインテーマといえば、『「嘘が見える」という自身の特殊能力と鹿乃子がどう向き合っていくか』だろう。
全回6話では、自分の能力を過信しすぎると偏狭的になってしまうことに気づかされた鹿乃子。
一回の失敗を引きずり、一時的に能力を活用することに抵抗を覚える鹿乃子だったが、左右馬の声掛けのおかげで、もう一度自分の能力を活用していこうと思えるようになったのだった…
…からの今回。
失敗を恐れず、他者の目を気にしすぎず、見えた「嘘」と真摯に向き合い、状況に合わせて自分なりに活用していこうと試みる鹿乃子。
そんな彼女の姿を見てる時、「うんうん。そうそう!それでいいぞ!鹿乃子!」と謎の親目線になる。
なのに!
次回8話予告を見ると、鹿乃子の特殊能力が消えてしまった…??
せっかく鹿乃子が積極的に「嘘」を活用していこうと前向きになってきたところだったのに…!!
いったいどうなるのか?
8話も楽しみです!
噓解きレトリック あらすじ&感想レビュー(8話)
8話 あらすじ
祝左右馬(鈴鹿央士)が留守中の探偵事務所に、端崎馨(味方良介)が来た。
馨は応対した浦部鹿乃子(松本穂香)に、スリや置き引きの注意喚起を促すビラ配りを手伝って欲しいと頼む。
馨は先日、駅で歳末警戒の強化を呼びかけていたところ、スリに遭ったと言う婦人に声をかけられた。
遠方に嫁いでいる娘のお産に駆けつけようとしたのだが、財布をスラれてしまい途方にくれていたのだ。
婦人の頼みに、馨は片道分の切符代を貸したと言う。
すると、そこに帰って来て話を聞いていた左右馬が寸借詐欺の手口だとピシャリ。
それでも、馨は連絡先も教えたと婦人を疑う様子はなかった。
そんな時、『くら田』で倉田達造(大倉孝二)と『八百六』の六平(今野浩喜)が喧嘩。
左右馬と鹿乃子はヨシ江(磯山さやか)とタロ(渋谷そらじ)に仲裁を頼まれる。
ことの原因は、六平が急に決まった寄り合いの弁当のお重を『くら田』に発注したことだった。
六平は十三折だと言うのだが、書き付けには廿三(二十三)折となっていて、達造はその数のお重を作ってしまった。
だが、六平は注文書にも十三折と書いたと譲らない。
左右馬は達造、六平、ヨシ江を一人ずつ事務所に呼んで事情を聞く。
すると、3人とも六平が注文時に言葉では「十三折」頼んでいたことが一致。
ヨシ江は六平が十三折と書くのも見ていた。
では、なぜ書き付けは廿三折なのだろうか?
誰かがウソを?
だが、鹿乃子の耳にも3人の話にウソは聞こえない。
もしかすると、自分にはウソが聞こえなくなってしまったではないかと鹿乃子は思い…。
引用元:Tver
8話 感想レビュー
これまでは「嘘が聞こえるという特殊能力さえなければ…!」と思っていた鹿乃子だったが、いざ「嘘が聞こえなくなったかも…?」となったら、急に怖くなってしまう。
不安に駆られた鹿乃子は、心の中でこんなことを思います。
この中のどれかが嘘だとしたら怖い…。
みんなは嘘がわからないのに、何を信じてどうやって判断するの?
いつもこんな不安の中で生きてるの?
たしかに、他人の嘘が聞こえない中で生きている私たち。
何を信じてどう判断して生きているのだろう?
当たり前のことすぎて深く考えたことがなかった。
そんな鹿乃子の問いに左右馬はこう答えます。
どんなに聞いても嘘か本当かわからないなら、まず何か信じて、傷つくの覚悟して飛び込んでみなきゃ始まんないでしょ?
傷つく覚悟で飛び込む。
たしかにその通りだ。
嘘をついているかどうかと疑心暗鬼になりすぎていたら何も始まらない。
嘘が聞こえない私たちは、傷つく覚悟でまずは信じる。
人づきあいが怖いと感じてしまう僕の心に刺さった。
噓解きレトリック あらすじ&感想レビュー(9話)
9話 あらすじ
祝左右馬(鈴鹿央士)の探偵事務所に藤島千代(片山友希)が来た。
仕事の依頼なのだが、かねてから千代を苦手とする左右馬は気乗りしない。
だが、浦部鹿乃子(松本穂香)が間を取り持ち、左右馬は藤島家の知り合いだという依頼主、実原久(余貴美子)と会うことに。
ほどなくして久が事務所を訪ねて来る。
気乗りしていなかった左右馬だが、久から目の前に依頼金を置かれた途端に乗り気になり、鹿乃子とともに久の依頼を聞くことに。
久は亡くなった娘の依里(吉田美佳子)の写真を左右馬と鹿乃子に見せた。
依里は25年前、久の夫の書生である山岡乙吉(濱田和馬)と恋に落ちる。
久の夫は怒って乙吉を追い出し、すぐに依里と別の男性との縁談を進めた。
しかし、結婚式当日に依里は乙吉と駆け落ちしてしまったのだ。
久は依里の行方を知りたかったが、久の夫は依里を探すことを許さなかった。
そんな中、久の夫が急な病で他界。
久が書斎を整理していると、依里の駆け落ち後を調査した書類が見つかった。
調査書によると、依里は小さな町で“山岡鶴子”と名乗って暮らしていた。
実原家の弁護士・神代(おかやまはじめ)は依里を探しに行くが、駆け落ちした後、乙吉は流行病で亡くなり、依里も一人の子どもを産んだ後に命を落としてしまっていた。
神代は、依里が残した子どもを探すために新聞広告を出すと、依里の一人息子だと名乗る徳田史郎(濱尾ノリタカ)と本条皐月(野村康太)が現れる。
久の依頼は、左右馬にどちらが依里の本当の子どもなのかを見極めてほしいというものだった。
うそがわかる鹿乃子は史郎がうそをついていることがすぐに分かるが、それを久たちにどのように証明すれば良いか頭を悩ます。
9話 感想レビュー
「嘘」がわかるから「本音」もわかる
実原久のお屋敷へ行く当日。
「そんな恰好じゃみっともなくてよ!」と乗り込んできた千代。
鹿乃子は生まれて初めてのメイクをしてもらい、千代の持参した洋服に着替えた。
しかし、恥ずかしさからなかなか2階から降りていけない鹿乃子。
千代に「鹿乃子さ~ん!」と呼ばれ、鹿乃子は恐る恐る階段を下りて行く。
階段下からひょっこり顔を出した左右馬。
左右馬は鹿乃子を見て一言。
「ほんとだ。かわいいねぇ鹿乃子くん。どうして降りてこないの?」
嘘のないその言葉を聞いて、
「なんでもないです」
と、笑顔で返す鹿乃子。
「嘘」がわかるということは、嘘ではない「本音」もわかるということ。
嬉しい言葉が「本音」だとわかったら、そりゃあ思わずニンマリしちゃいますよね。
恋愛とはまた違った、ゆるやかな男女の関係性。
「好き」とか「愛してる」とか言う恋愛ドラマからは得られない”幸福感”を得られます。
「背守り」が真相を解く鍵だった
出会った瞬間、「本当の孫は本条皐月ではないか?」と思っていたという久。
しかし皐月から、「僕を生む時、母が縫ってくれていた産着に”皐月の花のような背守りが縫ってあったんです」と、名前の由来を聞かされた久は、「やっぱり違う?」と悩んでいたそう。
背守りとは、子どもの着物に施された刺繍のことで、魔除けやお守りの意味が込められているんだとか。
なんでも、久もまた依里が産まれた時に背守りを縫っていて、その図柄は”鶴”だったらしい。
久は依里に「産着に鶴を縫った」ことを伝えており、その話を聞いた依里は「子どもが産まれた時は私も鶴を縫う」と言っていたらしい。
”鶴”を背守りに縫うと言っていたはずだから、”皐月の花”を縫うはずがない…。
と久は思ったそうだ。
その謎はすぐに解き明かされる。
実際に、赤子の頃皐月が着ていた産着に施されたのは”鶴”だったのだが、
依里があまりに不器用だったがために”皐月の花”に見えてしまったのだった。
ドラマとしてはだいぶ小さいオチだった。
けど実際の「謎」なんて、大抵こんなふうに大したオチでないことの方が多いわけで。
ほのぼのとした終わり方で良かった。
が。
では、依里の息子だと名乗り出た徳田史郎という男は何者だったのか…?
徳田史郎は何者だったのか?
結果的にその正体は明かされることはなかった。
ただし、徳田史郎はそもそも徳田史郎でもなかった。
徳田史郎という人物の経歴を乗っ取った別の誰かだったのだ。
そして、徳田史郎を名乗っていた謎の男は、去り際に「鹿乃子さん、今の僕の話はどっち?」と言って、鹿乃子が左右馬にする”嘘の合図”をやってみせた。
つまり、徳田史郎を名乗る謎の男は、鹿乃子の嘘が見える能力に気づいたのだろうか…?
Xでは、原作マンガの公式が、
「偽・史郎」が今後も二人に関わってくることをにおわせているが果たして?
噓解きレトリック あらすじ&感想レビュー(10話)
10話 あらすじ
九十九夜町に雪が降り、本格的な冬を迎えようとしている。
祝左右馬(鈴鹿央士)の探偵事務所で助手として働く浦部鹿乃子(松本穂香)は母のフミ(若村麻由美)宛の封書を郵便ポストに投函。
鹿乃子はこれまでもフミに近況を知らせる手紙を出していたが、この時、初めて事務所の住所を書いていた。
そのため、鹿乃子はフミからの返事を待つ。
左右馬は鹿乃子が手紙を待っていることに気づいた。
ある日、倉田タロ(渋谷そらじ)と会った鹿乃子は、「サンタクロースに何をお願いしたの?」と聞かれる。
「サンタクロース?」と聞き返す鹿乃子。
タロは鹿乃子がクリスマスを祝ったことがないと知って、あることを思いつく。
タロは母のヨシ江(磯山さやか)に、お食事処『くら田』で鹿乃子のためにクリスマス会を開くことを提案。
鹿乃子には内緒で、父の達造(大倉孝二)に料理を作ってもらい、左右馬はもちろん、端崎馨(味方良介)たちにも飾り付けを協力してもらう。
後に企画を聞かされた左右馬は渋い顔。
ウソを聞きわける力を持つ鹿乃子に内緒事は難しいからだ。
一方の鹿乃子は、町で探偵依頼を求めるビラ貼り。
掲示板にビラを貼っていると、書店から嘉助(黒川想矢)を追って、利市(橋本淳)が飛び出してきた。
利市から嘉助を捕まえる手助けを頼まれた鹿乃子は応じる。
左右馬はつくも焼き屋のじいさん(花王おさむ)が寺へ屋台を出すので、寺までの屋台引きを手伝いがてら、稲荷を掃除。すると婦人に声をかけられた。
祝探偵事務所への行き方を尋ねる婦人に左右馬は鹿乃子の母・フミだとわかり…。
引用元:Tver
10話 感想レビュー
「嘘がわかる」ということは「本当がわかる」ということ
鹿乃子の「嘘がわかる」という特殊能力は、
嘘をついた人にとっては厄介で迷惑な能力ですが、
逆に、真実を話しているのに信じてもらえない人にとっては、救われるこもともある能力である。
10話のエピソードは、そのことを明示していましたね。
【利市と嘉助と鹿乃子のエピソード】
お世話になっている店の本が破けてしまい、店の旦那にバレる前に、破けたのと同じ本を買いに本屋へやって来た嘉助。
しかし、手持ちのお金ではその本を購入できそうにもなかった。
そこへ利市がやって来る。
嘉助のことを本屋の店員だと勘違いした利市は、「この本あるか?」と声をかける。
嘉助は咄嗟に本屋の店員のフリをして、「これなら奥に在庫があるから取ってくる。その前に先にお代を」と言って、利市からお金をくすねて逃亡。
たまたまその近くに居合わせた鹿乃子も利市と一緒になって逃亡する嘉助を追いかけることに。
ほどなくして利市たちに捕まってしまう嘉助。
「どうしてこんなことをしたんだ?」と利市に問われた嘉助は、「旦那さんの本が破れてしまって…」と事情を話しだします。
利市「本破いたのはちゃーんと謝らねぇと」
嘉助「俺じゃねーよ!どっかの野良犬がいつの間にか上がり込んでて破いたんだ」
利市「じゃあ、そう言えばいーだろ」
嘉助「どうせ信じてもらえない」
利市「なんで?」
嘉助「…死んだ父ちゃんが物取りで捕まったやつだから」
嘉助「前の店でもなんかあったらいっつも俺のせいになってた。本当のこと言ってもいつも信じてもらえねぇんだよ。だったら最初っから嘘で騙すしかねぇんだよ!」
利市「随分とまぁ拗ねてるなぁ。で、いくら足りねぇの」
嘉助「は?」
利市「全部は無理だけど、ちょっとは出してやれるから」
嘉助「何言ってんだあんた。今の話しだって嘘かもしんねーぜ?」
鹿乃子「嘘じゃないです!」
嘉助「…嘘でもそう言ってもらえりゃ、嬉しいもんだな」
鹿乃子「嘘じゃないです…」
この会話からもわかるように、嘉助は父親の件で無条件に人から信用されない人生を送ってきた。
いくら本当のことを言っても信じてもらえない状況が続けば、「本当のことを言って無駄だ」という気持ちになってしまうものです。
信じてくれる人がいること、ただそれだけで救われる人もいる。
鹿乃子の「嘘じゃないです!」と言う言葉は、嘉助の心を救ったのだと思います。
【左右馬と鹿乃子の母のエピソード】
鹿乃子のいる九十九夜町を訪ねにやって来た鹿乃子の母。
しかし母は道に迷ってしまい、なかなか九十九夜町にたどり着けない。
その時、たまたま稲荷神社の掃除をしてい左右馬に「九十九夜町へはどう行けば…?祝探偵事務所という所をご存じで?」と道を尋ねる。
左右馬は、声をかけてきた女性が鹿乃子の母親だと気づくが、あえて自身の正体を明かさず話を聞くことにした。
「娘と会う気はない」と語る鹿乃子の母に、左右馬はこんな話をします。
母「怖いんです」
左右馬「娘さんと会うのが?大切な娘なのに?」
母「大切だから、私の言葉であの子を傷つけるんじゃないかって思って」
左右馬「傷つくことを言わなければいいじゃないですか」
母「…」
左右馬「もしも娘さんに嘘がわかる力なんてあったら、そうやって悩むのもわかりますけどね」
母「へ?」
左右馬「自分の言葉に嘘が混ざっていたら、それを聞かれてしまったら、そう思って怖くなるでしょう?」
左右馬は、自らの正体を明かした後、鹿乃子の母にこんな話をします。
左右馬「どうして祝先生は鹿子とうまくやれるのか?ですが、僕は嘘を暴かれるより、本当のことを信じてもらえない方が面倒なんです。だって嘘がわかるってことは本当がわかるって事でしょ?」
母「そんな風に考えたことなかった。傷つけないようにって取り繕って。嘘にならないようにって。でもそれがかえって嘘になるんじゃないかしらって、そういうこと考えてばっかり」
左右馬「そういうこと考えないで、本当の気持ちを全部伝えればいいじゃないですか」
嘘には「相手のためにつく優しい嘘」もあります。
鹿乃子の母は、「鹿乃子を想ってつく嘘」を鹿乃子が誤解して受け取ってしまうのではないか、と恐れていました。
対して左右馬は、「嘘を暴かれること」を怖いと思っていなくて、
逆に「本当のことを信じてもらえない方が面倒」だと常々思っていました。
人から信じてもらえないという点で嘉助と似ていますね。
だからこそ、鹿乃子の能力にいつも救われていたわけですね。
2つのエピソードからわかるように、
鹿乃子の「嘘がわかる」という能力は、「真実を信じてもらえない人」にとって救いになる能力なのです。
本当のことを言うのはみんな怖い
今回、2つのエピソードですごく気になった会話がある。
嘉助「今の旦那さん、いい人なんだ。ちゃんと話したら信じてもらえるかな?」
利市「それはわかんねぇよ。俺は旦那じゃねぇし」
嘉助「まあいいや。信じてもらえなくても話してみる。なんでかそんな気になった」
母「そんな風に考えたことなかった。傷つけないようにって取り繕って。嘘にならないようにって。でもそれがかえって嘘になるんじゃないかしらって、そういうこと考えてばっかり」
左右馬「そういうこと考えないで、本当の気持ちを全部伝えればいいじゃないですか」
母「許してくれるでしょうか?今さら」
左右馬「さあ?僕は鹿乃子くんじゃないので」
母「…」
左右馬「でも、僕の知ってる鹿乃子くんはちゃんと全部聞いてくれる人ですよ」
嘉助も鹿乃子の母も、自分の正直な気持ちを伝えたら相手がどう受け取るかということを、ひどく気にしていました。
それに対して利市も左右馬も、「さあ?僕はその人じゃないのでわからない」と同じように返答しています。
自分の気持ちを伝えたら、相手からどんな反応が返ってくるかはわからない。
でも、それを怖がっていたら一生分かり合うことなんかできない。
だから怖いかもしれないけど、自分の気持ちを正直に話してみて。
そんな作者の伝えたい意図を感じました。
噓解きレトリック あらすじ&感想レビュー(最終話)
最終話 あらすじ
稲荷の掃除をして帰って来た祝左右馬(鈴鹿央士)と浦部鹿乃子(松本穂香)。
二人が探偵事務所に戻ると、女性に声をかけられる。
女性は行き場所も金もなく困っていたら、祝探偵事務所の大家に会い、事務所に住んで良いと言われたと話す。
鹿乃子の耳には女性の言葉にウソは聞こえなかったが、左右馬は泊まる部屋がないと渋る。
すると、女性は大家からだと左右馬に手紙を渡した。
手紙には“彼女を泊めたらたまっている家賃をなしにする”とあった。
事務所に見知らぬ女性が泊まることに不安を感じる鹿乃子だが、左右馬が断るはずもない。
話がまとまると、女性は二人に青木麗子(加藤小夏)と名乗った。
しかし、その名前は嘘だった。
左右馬たちが麗子を連れて『くら田』に行くと、店にいた六平(今野浩喜)が麗子を見て美人だなどと褒めそやし酒を酌み交わし始めた。
二人の会話を聞いていた鹿乃子は、麗子が自身の境遇を話す言葉にウソを聞く。
そんな中で急に左右馬が鹿乃子に「鈴蘭って、夏の花だよね?」と尋ねる。
梅雨前に咲く花だと答える鹿乃子。
左右馬は麗子がしていた冬用の手袋に鈴蘭の刺繍がある事を疑問に思ったようだ。
事務所に帰った左右馬は麗子に早く出ていってもらうための作戦を画策。
そこで左右馬は、まず「青木麗子という名前、ウソですよね?」と麗子に突きつけた。
彼女は否定せず「本当の私は誰にも秘密」と返し、自分自身のことをすべてウソで語る。
そんなところに、端崎馨(味方良介)が来て左右馬を連れ出した。
麗子と二人きりになった鹿乃子は、話すうちに、どうやら麗子は失恋をして家を出てきたのではないかと推理する。
引用元:Tver
最終話 感想レビュー
嘘には、つく人の願望がある
麗子と名乗っていた女の本名は蘭子でした。
身寄りのいなかった蘭子は、幼い頃から鈴乃の屋敷で女中として働いていたのです。
同い年の鈴乃に仕えるうち、蘭子は鈴乃に恋をしていました。
鈴乃は隣の家に住む鈴村家のご子息と婚約することになり、そのことを知った蘭子は、「素直に鈴乃の幸せを喜べない」と、鈴乃の家から出て行ってしまったのでした。
蘭子は帰れない理由をこう語ります。
「気づいたの。私が幸せを願ってたのは嘘だったんだって。
お嬢さんの幸せを願えない自分が、もう心底イヤになった。
大切なお嬢さんにこんな醜い本当を見せたくないし、心にもない嘘をつきたくないの」
そんな彼女に向かって左右馬はこんな言葉をかけます。
左右馬「嘘でしか幸せを願いないなら、ずっと嘘ついてりゃいいんじゃないですか?」
蘭子「え?」
左右馬「なんでもそう簡単に自分の思い通りにはなりませんよ。
たとえそれがあなた自身の心でもね。
何もかも思い通りになるなら誰も嘘なんかつかない。
思いり通りにならないものを、思い通りにしようとしたとき嘘をつくんです。
こうだったらいいとか、こう思ってほしいとか。
”ただ事実ではない”ということだけではなく、嘘には、つく人の願望がある。欲がある。願いがある。
あなたが嘘をついたのは、鈴乃さんの幸せを願えないからだけじゃなくて、それでも願いたいからなんじゃないですか?鈴乃さんの幸せを」
「相手の幸せを願いたい」けど願えない。
片想いだったらよくあることですよね。
でも、「相手の幸せを願いたい」という願望があるからこそ嘘をつくんだと左右馬は言いたいんですね。
左右馬の話を聞いた蘭子はこう答えます。
蘭子「ほんとね~。願えないけど、願えたらいいのに。私面倒くさ!」
左右馬「こっちのセリフです。鈴乃さんのところに戻って嘘をつき続けるのは嫌ですか?」
蘭子「イヤよ。…なんてね。つくよ、嘘。心を込めて」
「鈴乃の幸せを願いたい」から心を込めて嘘をつくと決めた蘭子。
後日、蘭子は鈴乃の屋敷に戻り、
心を込めて「二人の幸せをずっと願ってる」と嘘をつくのですが、そのシーンがとても切なかったです。
鹿乃子は、蘭子が鈴乃に嘘をつく姿を見ながら、過去の嘘をついた人たちも思い出しながら、こんなことを思います。
嘘をつくことでしか見えないものがあるのだとしたら、私の耳に聞こえてくるのは、そんな人の願いなのかもしれません。
自分の手柄を立てたい。相手を出し抜きたい。嫌われたくない。相手を喜ばせたい。自分を良く魅せたい。幸せにしたい。
人が嘘をつくとき、そこには良くも悪くも「願い」があります。
鹿乃子の耳に聞こえるのは「願い」のすえにつく「嘘」だったのですね。